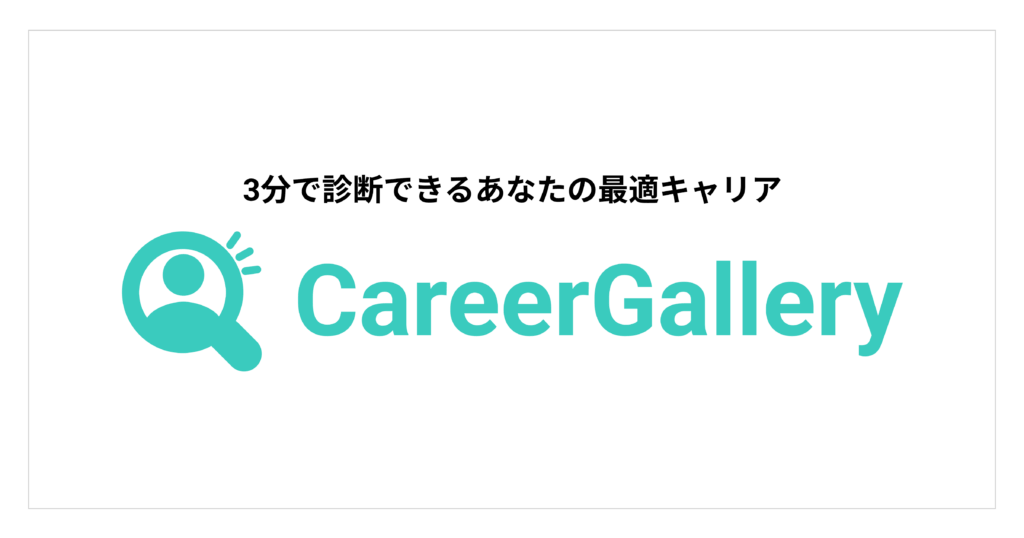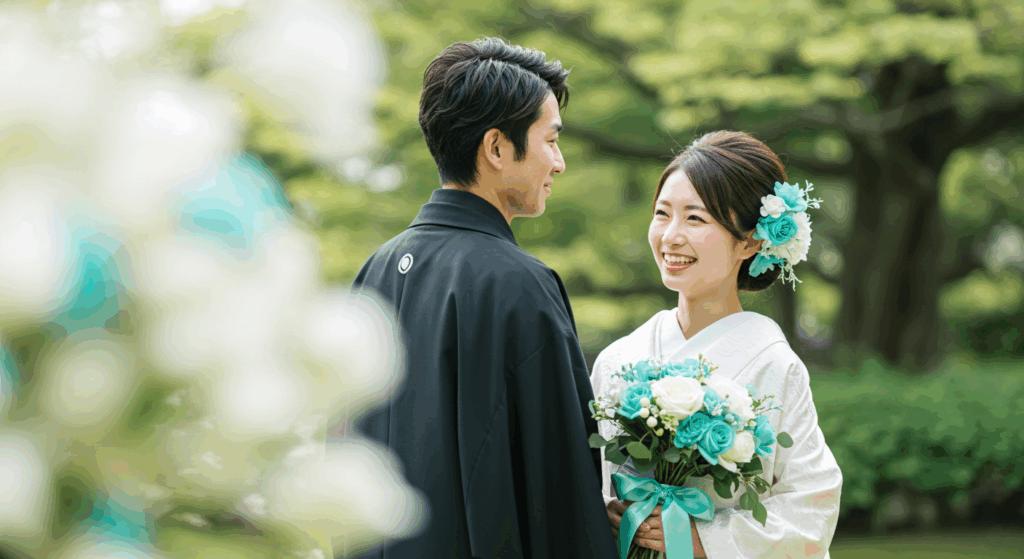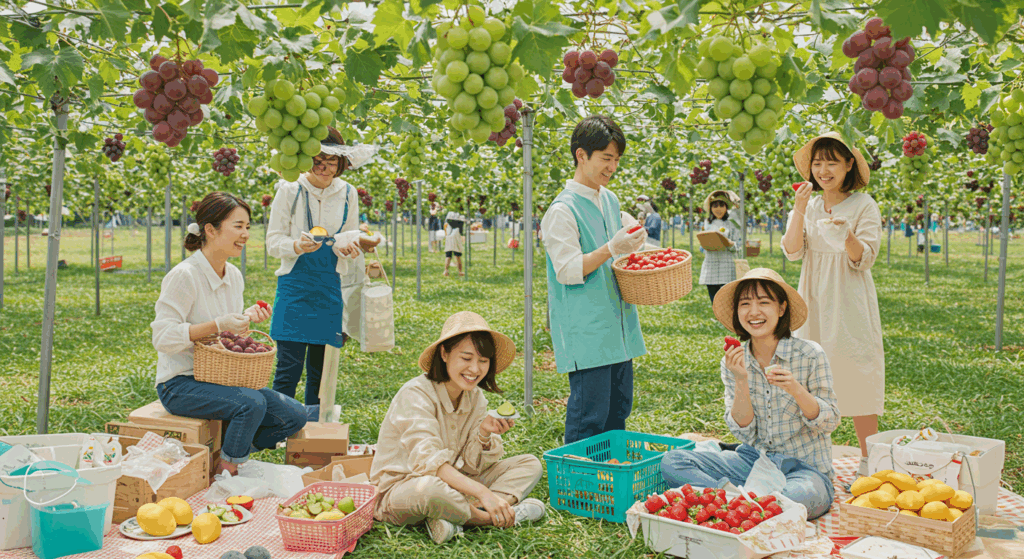「もっと稼がなきゃ」「年収を上げなきゃ」そんな思いが常に頭をよぎる方へ。実は、収入と幸福感の関係には、思っている以上に“曲線”があります。本記事では、OECD(経済協力開発機構)や各種研究のデータをもとに、稼ぐこと=幸福につながるかどうかを再検討します。
「収入が上がれば幸福が上がる」わけではない
まず初めに。年収を上げることは幸福の必要条件かもしれないが、十分条件ではないというデータがあります。
-
OECDの資料によると、2021-22年時点で加盟国の平均「生活満足度(Life satisfaction)」は6.7/10でした。(参照元:OECD Life satisfaction)
-
収入と幸福感の相関は観察されており、例えば「所得が高いほど平均的に幸福度も高い」という傾向はあります。(参照元:Our World in Data : Happiness and Life Satisfaction)
-
しかし、研究「Income and the sense of happiness …」では、ポーランドの調査で「一定水準(PLN 3,000)を超えると、収入の増加が幸福感の増加に比例しなくなる」といった結果が出ています。(参照元:Income and the sense of happiness in the light of empirical research)
-
また、所得格差(income inequality)が大きい国ほど幸福度が低いというデータもあります。(参照元:Economic Freedom, Income Inequality and Life Satisfaction in OECD Countries)
これらを総合すると、「年収を上げることは幸福の必要条件かもしれないが、十分条件ではない」という構図が浮かび上がります。
幸福の定義はお金ではなくメンタル
なぜ、収入がある程度まで増えても幸福感があがらないのでしょうか?その背景には、次のような構造があります。
-
物質的な安心(住まい・暮らし・生活基盤)が整うと、収入増のインパクトが相対的に小さくなる。
-
人とのつながり・自由な選択・健康・時間といった「非物質的価値」が幸福に寄与する割合が高い。たとえば、OECDによる「What matters the most to people?」という調査では、自由に選べること・健康であること・社会的つながりが幸福に大きく影響する要因とされています。(参照元:OECD What matters the most to people?)
-
世代・国・文化によって「豊かさ」の捉え方が変化しており、「稼ぐこと=価値」という定義から脱却する動きも広がっています。
したがって、収入を増やすこと自体を目的化するのではなく、「そのお金で何を実現したいか」「どんな時間を得たいか」を問い直すことが、次のステージに進むための鍵となります。
「稼ぐ目的」を再定義するための3つの問い
ここからは、読者が自身の「お金と幸福」の関係を見直すためのセルフリフレクションとして、次の3つの問いをご提示します。
問い①:この年収が上がったとき、真っ先に変えたいこと/手に入れたいものは何か?
→ 例えば「家を買いたい」「旅行に行きたい」「時間を増やしたい」など。目的が明確であれば、収入増が手段になります。
問い②:もし年収が変わらなかったとしても、今と同じ“幸福”を感じられるか?
→ 収入によらない幸福軸(人間関係、趣味、自己成長など)を扱う視点になります。
問い③:収入を増やすために、何を“犠牲”にしているか?その犠牲を払ってまで得たい価値は何か?
→ 長時間労働・健康・人間関係・自由時間など、トレードオフを可視化することで「稼ぐこと」に伴う代償を理解できます。
まとめ
稼ぐこと自体は、否定されるものではありません。むしろ、それによって得られる安心感・選択肢・自由は確かに価値があります。
しかし、「もっと稼がなきゃ」という思いが焦り・疲れに変わっているのであれば、是非「何のために稼ぐのか」を問い直してみてください。
データが示すように、収入が幸福を無限に保証するわけではなく、ある一定を超えると“別の価値”が幸福感を支える土台になります。
あなたのお金は、あなたの人生の“何を支えているか”。その問いを、今この瞬間、立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。