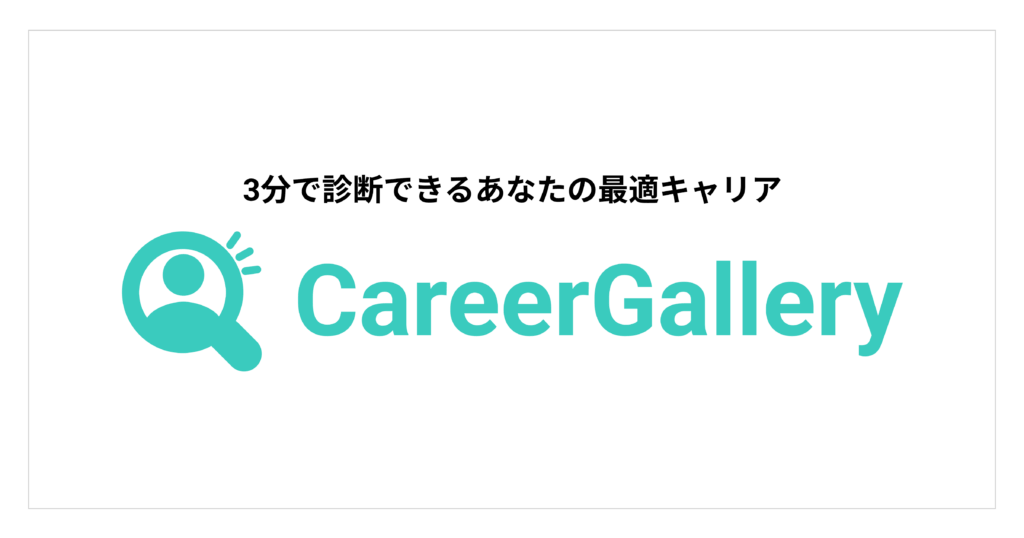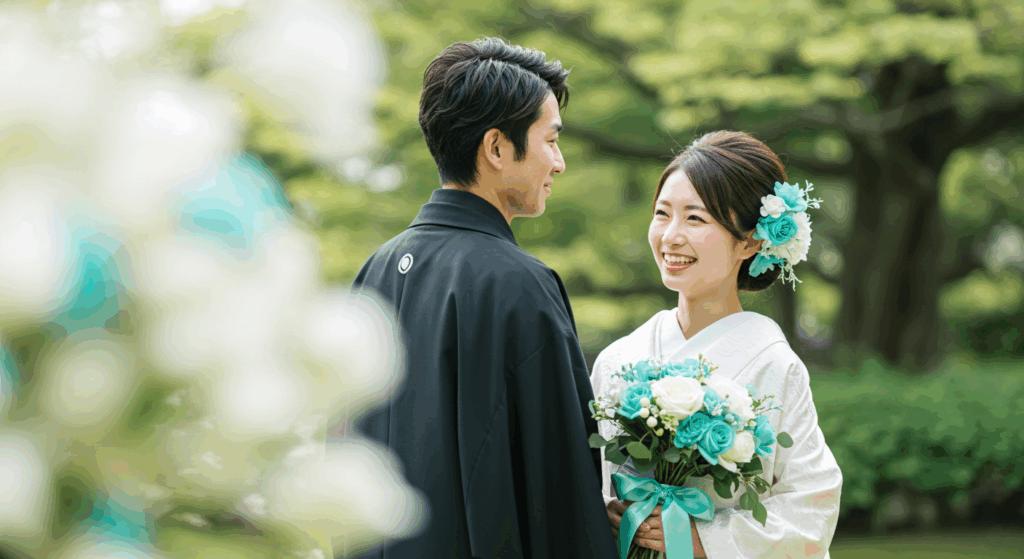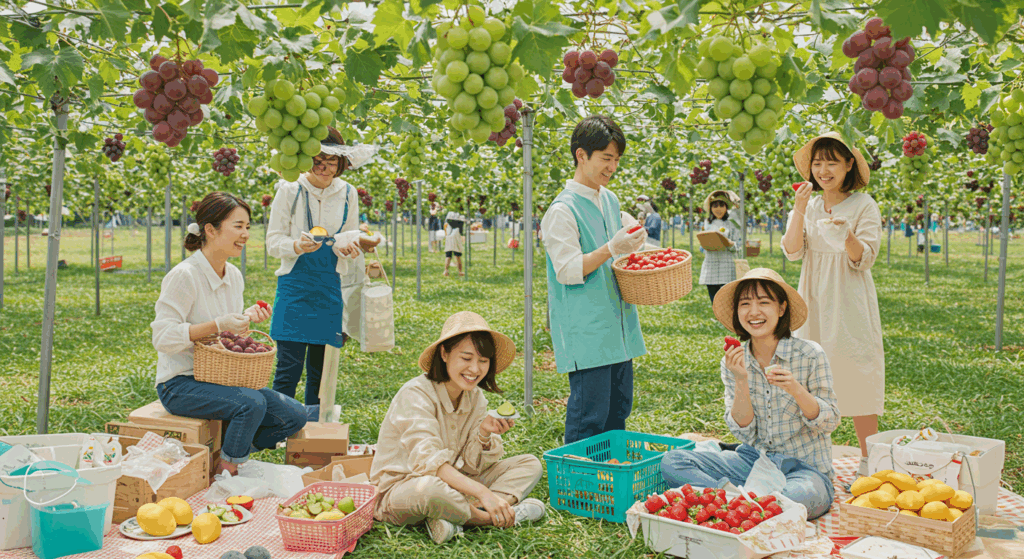子どもが生まれても、仕事も家庭も全力でやりたい。そう思っていたあなたが、ふと「自分は父親として正しい関わり方をしているのだろうか」「子育てと仕事を両立できるのか」と迷う瞬間があるかもしれません。実はこの迷いは、あなた一人のものではありません。社会構造・制度・価値観の変化とともに、父親役割への期待も変わってきているのです。
本記事では、最新の統計データをもとに「子育てに迷うパパ」が陥りやすい背景を明らかにしつつ、具体的な関わり方や考え方を提示します。
父親育児への意識と実態
まずは、父親の育児参加・家事負担に関する最新データを押さえましょう。現実を知ることで、あなたの迷いが「自分だけの問題」ではなく、社会構造・制度にも起因するものだと認識できます。
◼ 育児休業取得率におけるギャップ
男性が育休期間を「取得できるか否か」「取得期間」が揺れ動いており、制度利用のハードルが依然として存在します。
- 令和5年度の調査では、男性の育児休業取得率は 30.1% にとどまり、女性(84.1%)とは大きな差がある。(参照元:厚生労働省 令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について)
- とはいえ、この数字は前年(17.13%)から +13%と上昇傾向。(参照元:厚生労働省 2023年度「雇用均等基本調査」結果)
- また、令和6年度調査では 男性の取得率が40.5% にまで達したとの速報も出ており、制度の変化が実を結いつつあります。(参照元:厚生労働省 令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について)ただし、男性の育休取得期間は依然として短く、「2週間未満」が約4割を占めるという報告も。 
◼ 家事・育児時間における男女差
夫側の関与時間は確実に増えつつあるものの、妻の比と比べると依然として低水準です。
- 総務省の調査によれば、6歳未満児を持つ家庭における夫の家事・育児関連時間は 1時間23分/日(約83分)。対して妻は 7時間34分(約454分) に達するという報告もあります。(参照元:6歳児未満児のいる夫の家事・育児関連時間)
- また、内閣府の資料では、日本の夫婦間における家事・育児負担の割合は、夫:妻 ≒ 15:85 程度という指摘もあります。(参照元:男性の「家庭進出」は、家庭にも社会にもいいこと尽くめ! 『「家族の幸せ」の経済学』著者・山口慎太郎さんが解説)
- さらに、国立社会保障・人口問題研究所の調査では、平日に2時間以上家事をする夫は少なく、8割以上が「2時間未満」にとどまるという結果も示されています。(参照元:2022年社会保障・人口問題基本調査)
◼ 家事・育児時間の推移と制度作用
夫の関与を増やすことは、家庭の安定や妻の就業継続にも好影響を与えうるのです。
- 長期的には、夫の家事・育児関連時間は増加傾向。たとえば休日の家事・育児時間は、1996年 58.9分 → 2006年 109.1分と拡大しています。(参照元:神戸学院大学現代社会学部 休日における夫の家事・育児動向の時系列的推移)
- しかしながら、この増加率を見ても妻との時間差は縮まりきらず、構造的な差が根強く残っていることが示されています。(参照元:男女共同参画局 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート)
- 特筆すべきは、夫の家事・育児時間が長い家庭では、妻の継続就業率や第2子以降の出生率にもプラスの相関が見られるという研究もあります。(参照元:女性の継続就業・出産と男性の家事・育児時間の関係)
なぜパパは子育てに迷うのか ── 心理・制度・価値観の重層構造
統計だけでは「なぜ迷うか」が説明できないことも多いです。ここでは、心理・制度・文化の3軸から、なぜ男性の子育てに“迷い”が生まれるかを掘り下げます。

◼ 期待とギャップ:理想父親像のプレッシャー
- メディアやSNSで見える「できる父親像」は、日常で実現するにはハードルが高いことが多い
- そのギャップが「自分はまだ足りない」と焦り・葛藤を生む
◼ 制度利用しづらさ・評価への不安
- 育休制度があっても、取得しづらい職場文化や昇進・評価への懸念が障壁になる
- また、職場が取得率を公表する義務が拡大されているものの、実質的運用が追いついていないケースもあります。 (参照元:男性の育児休業取得率等の公表について)
- 制度は「ある」けれど「使えるか」は別問題
◼ 時間制約と仕事のプレッシャー
- 長時間勤務や通勤など、仕事負荷が重いと、帰宅後に子育てをする余力が削られる
- ただし興味深い統計もあり、「労働時間が短いから育児参加できる」とは限らない、という調査もあります。(参照元:「労働時間が長くて家事・育児ができない」は大ウソ…最新調査でわかった日本の男性が家事をしない本当の理由)
つまり、時間だけでは説明できない心理的・文化的要因も大きく絡んでいるのです。
子育てに迷うパパができること
迷ってしまう時期こそ、完璧を求めずにできる範囲から関わる実践が大切。ここでは、日常で取り入れやすい関わり方と、関係を育てる視点を示します。
1. 朝・夜の5分関与
例:起きた後の「おはよう」を言う、寝る前の読み聞かせなど。量より「関わろうとした意思」が子どもに伝わる。
2. 感謝と言語化
ママと役割分担の話をする前に、「ありがとう」を伝える。信頼感・協力関係を育てる基盤になる。
3. 情報・体験の共有
SNSや情報をそのまま鵜呑みにせず、「我が家流にカスタマイズ」する視点を持つ。
4. 代替案と休息を許すルール化
疲れたときは代替を頼む・休める仕組みをつくる。無理を重ねないことこそ継続の鍵。
5. 家事育児時間を少しずつ拡張する意識
調査が示すように、夫の関与が1時間程度でも、妻の継続就業率を支えることがあります。
まとめ
父親として子育てに迷うことは、あなた一人の課題ではありません。統計が示す通り、パパ育児の壁は制度・時間・文化の複層的な構造の中にあります。だからこそ、完全を目指すのではなく、自分なりの関わり方をコツコツ築いていくことが大事です。
もし「どんな育児アイデアを実際に他のパパが使っているか」「子育てを楽しむ工夫を見たい」と思うなら、ChildrenGallery をぜひ覗いてみてください。リアルな育児アイデアが詰まったメディアとして、あなたの子育てを後押しします👇